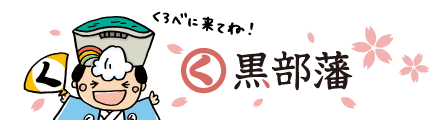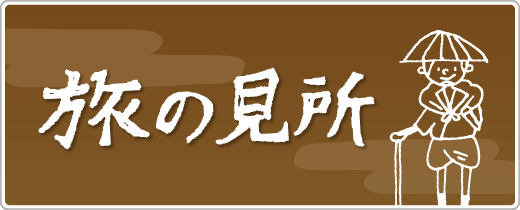神様を家に迎える行事

黒部市宇奈月町下立(おりたて)地区をはじめとする黒部川扇状地の各農村では、家庭ごとに「おおべっさま」をお迎えし、一番風呂や山海のごちそうでおもてなしするという行事が昔から行われとります。「おおべっさま」というのは恵比寿様と大黒様のことで、この地域で信仰されている身近な神様。元々は田を守る神として信仰されとったため、その年の収穫に感謝し、翌年の豊作を願うという意味があったがです。
11月20日になると「おおべっさま」が出稼ぎから帰ってこられます。感謝をこめてたくさんの料理を準備し、まるでそこに神様がおられるように「おかえりなさい」「ゆっくり休んでください」と声をかけながらおもてなしされるがです。そして、2か月後の1月20日早朝に、お迎えした時と同じようにごちそうを振る舞って送り出されるがです。ただ、お家に滞在しているとは言っても、生活の中で「おおべっさま」の存在を意識しすぎることはないがだそうです。それだけ当たり前のような存在で、親しみを感じる神様ながですね。

礼を尽くしておもてなし

11月20日の夕方は、玄関の戸を開けておき「おおべっさま」をお出迎え。電車が走るようになってからは、近くの駅までお迎えに行ったりもしとられたとか!
部屋で休まれた後は、お風呂へとご案内。「湯加減はいかがですか?」と、実際にご入浴されているかのように聞いたりもされます。その間に御膳を用意し、上がられたらお食事の時間。赤飯、カマスの味噌汁、腹合わせ(2匹)の鯛、二股大根、刺身、煮物などをお供えし、お酒もご用意されるがです。御膳には、煮物に入れる野菜は豊作を表す意味で大きめに切る、神様が召し上がるものだから味見はしない、という決め事もあるがだそうです。
この行事は各家庭で行われ、そのやり方は親から子へと伝えられとります。そのため、下立地区の中でもそれぞれの家で微妙な違いがあるがだとか。年によっては簡略化したり、新しいことを試みたり…ということもあって、必ずしも毎年同じということもありません。また、昔はまず囲炉裏のところで暖をとって休んでもらっていたのが、今は囲炉裏そのものがなくなり、やり方を変えざるをえない部分もあるがだそうです。でも、時代とともに少しずつ変わっていくところはあったとしても、帰ってこられた神様を精一杯おもてなしする姿勢は変わらんがです。形式よりもその精神を大事にして、行事が続けられとるがですよ。
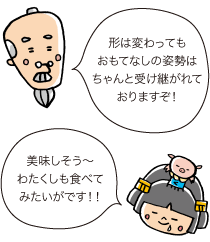
感謝の心をつないで
おおべっさま迎えがいつごろから始まったものか、はっきりとしたことはわかっとらんがです。似たような行事が能登(石川県)でも行われとるそうで、江戸時代に愛本橋の大工事があった際、それがこの地域に伝えられたとする説もあります。また、今回取材させていただいた柳原家では、使用する輪島塗の盃(さかずき)が入った箱に「明治5年」という記載があり、少なくとも明治の初めには行われていたがだろうと推測されます。
このように長く続いてきた行事ではありますが、つないでいくとなるとご苦労も多々あるがです。それぞれの家での伝承であるため、後継者がいないと途絶えてしまったり、代替わりを機にやめてしまわれたり…。食材の調達にも苦労することがあり、特に鯛は魚屋さんに予約していても、ちょうどいい大きさのものはなかなか手に入らないこともあるがだとか。そういう時は生の鯛の代わりに細工蒲鉾の鯛を使うなど、機転を利かせて乗り切ったこともあるがだそうです。
住民同士でも意外と他の家でどのように行われているか知らなかったりもするので、下立公民館では、おおべっさま迎えを解説する教室を開くなどして、次の代への継承を後押しされとります。きっと神様も毎年心待ちにしとられると思うがで、ご苦労も多いかと思うがですけど、心温まるこの交流をこれからも伝え続けていただきたいですね♪


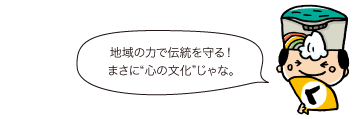
【おおべっさま迎え】
(国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財[越中の田の神行事])
●開催日
毎年11月20日
●開催場所
黒部市宇奈月町下立地区
※各家庭での行事のため、原則非公開です。
●アクセス
黒部市立下立公民館(黒部市宇奈月町下立3118)
電車で/
富山地方鉄道「下立駅」下車、徒歩3分
北陸新幹線「黒部宇奈月温泉駅」下車、車で10分
自動車で/
北陸自動車道「黒部IC」から車で10分
●地図
GoogleMapで詳しくみる。
(2025年11月14日)